どうも、太陽です。
最近話題になっている「VibeCoding」。コードがわからない初心者でもWeb制作やアプリ開発ができる──そんな期待を込めて、実際に触ってみた。
結論から言えば、「期待していたほどではなかった」。
作れるものの品質は50点〜70点止まり。これをいくら量産したところで、商売の世界では通用しないのが現実だ。
商売で通用するのは95点以上の“プロ品質”
Web制作やLP制作、アプリ開発の世界で、本当に価値があるのは95点以上のクオリティ。
確かに、個人ブロガーのような立場なら70点レベルでも問題ないかもしれない。しかし、ブログというビジネスモデル自体が現在では“ジリ貧”状態。
つまり、70点で通用する分野そのものが縮小している。
VibeCodingは「新たな金のなる木」ではなかった
イケハヤ氏が主宰するVibeCodingサロン(買い切り4980円)には2000人以上が参加しており、一見「熱気」があるように見える。
だが、実際に触れてみた自分としては「思ったよりも凡庸」という印象を拭えなかった。
最近の自分は、新しいツールに飛びつくのは早いが、見切りをつけるのも早い。
VibeCodingには可能性を感じたが、現実は“及第点”止まりだった。
将来的にプロ品質AIが到来するのか? 今は疑問
AIの進化は急速であり、いずれはプロ品質(95点以上)のサイトやアプリを自動生成できる世界が来るかもしれない。
しかし、「それが本当に訪れるのか?」と問われれば、現時点では懐疑的だ。
というのも、現在のAIコーディングは「数秒で70点のものを出力 → 人間が手直しして95点にする」という構想があるが、それすらうまくいっていないというデータがある。
AIツールは逆に“生産性を落としている”という研究結果
以下の調査によると、AIコーディングツール「Cursor」で出力されたコードのうち、実際に開発者が使用したのは39%。
しかもその39%のコードも、そのまま使われているわけではなく、人の手でレビューや修正が加えられている。
AIコーディングツールは生産性を19%も低下させているという調査結果、AI出力の評価・手直し・再出力などで無駄な時間が大量発生か
さらに興味深いのは、「AIを使うとタスク完了が実際には19%遅くなる」という点。
それにもかかわらず、開発者自身は「20%速くなった」と“錯覚”していたという。
AIの生産性に関する認識と、実際の効果にはギャップがあるのが現状だ。
AIコーディング=プロの仕事を奪う道具ではない(今のところ)
プロ品質(95点以上)を人間が出すには、知識・技術・経験が必要だ。
AIはそれを“補助”するツールではあっても、“完全代替”にはほど遠い。
とはいえ、実際の現場ではCursorやClaudeCodeを使って、「作業がかなり楽になった」という声もある。
スキルのあるプロが使えば、AIは有効。だが、初心者が頼るにはまだ厳しい段階だ。
VibeCodingは70点が限界、伸びしろは勉強次第
現状のVibeCodingは「コードがまったくわからない初心者でも、最低限の仕組みさえ理解していれば、70点レベルのものが作れる」ツール。
ただし、その70点で勝負できる市場は狭く、プロ品質(95点以上)が求められる現場では通用しない。
とはいえ、学習を積めば90点以上の領域には到達可能だろう。最低でも半年〜1年以上はかかるだろうが、努力次第ではプロに近づける。
ちなみに、WordPressの有料テーマなら80点レベルのサイトを作ることはできる。ただ、そこからの“伸びしろ”が乏しい。
VibeCodingの“ビジネスモデル”にも疑問
VibeCodingサロンに集まった2000人以上の参加者。その売上は1,000万円以上になるが、内容としては「初心者が70点のサイトを作れるようになる」ことが中心。
はっきり言ってしまえば、釣られて集まった人がいて、儲かるのはイケハヤ氏だけ──という構造になっている。
もちろん、これも資本主義の一部だ。
誠実で高品質なビジネスだけが成功するとは限らない。一時的であっても、邪道であっても、金は稼げる。そして「価格以下の価値」でも買われてしまえば、成立してしまう。
資本主義の限界がここにある。
金を大量に稼いだ者が、正義でも善人でもなく、「この仕組みの中で勝った」だけにすぎない。
Grok4やClaudeCodeに希望はあるか?
最近注目されている「Grok4」は、VibeCodingで作れる70点品質のものを、80点レベルに引き上げる可能性があるかもしれない。
また、ClaudeCodeのような生成AIツールも、以下の中国製を使えば課金する必要がなくなるかもしれない。
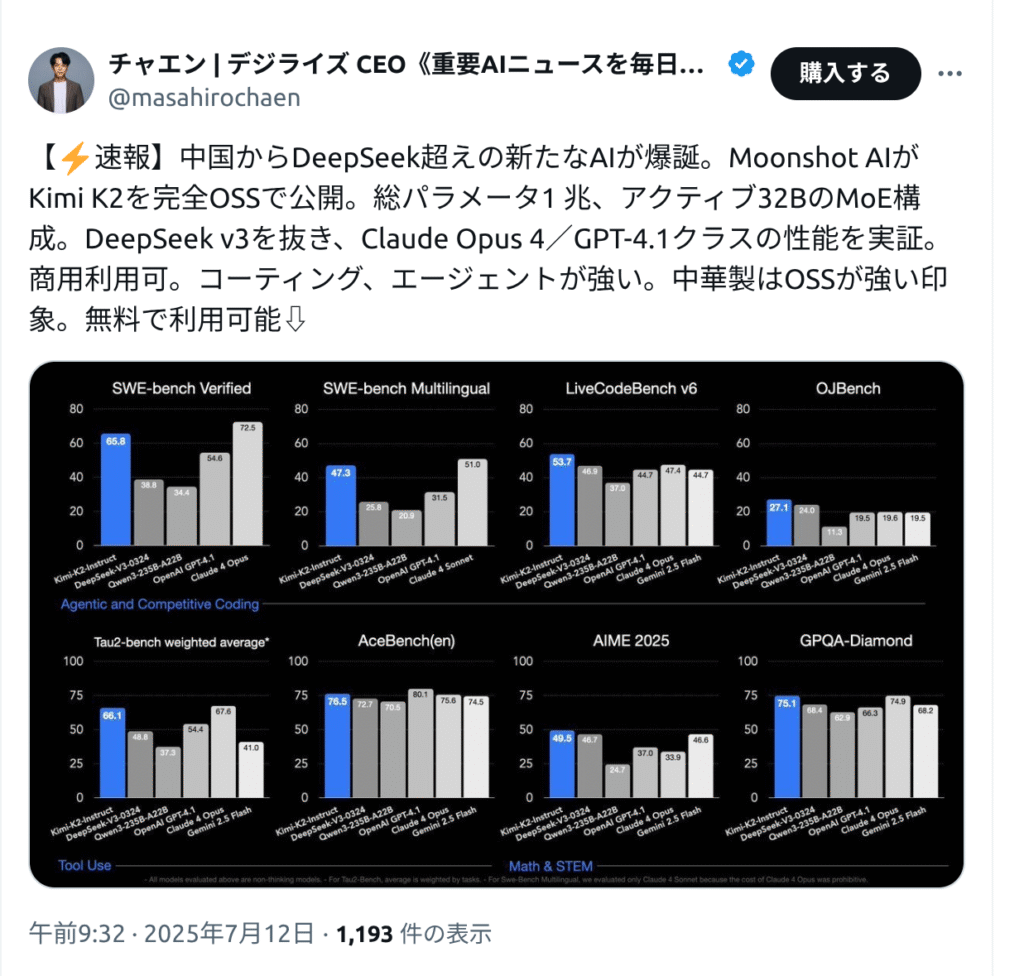
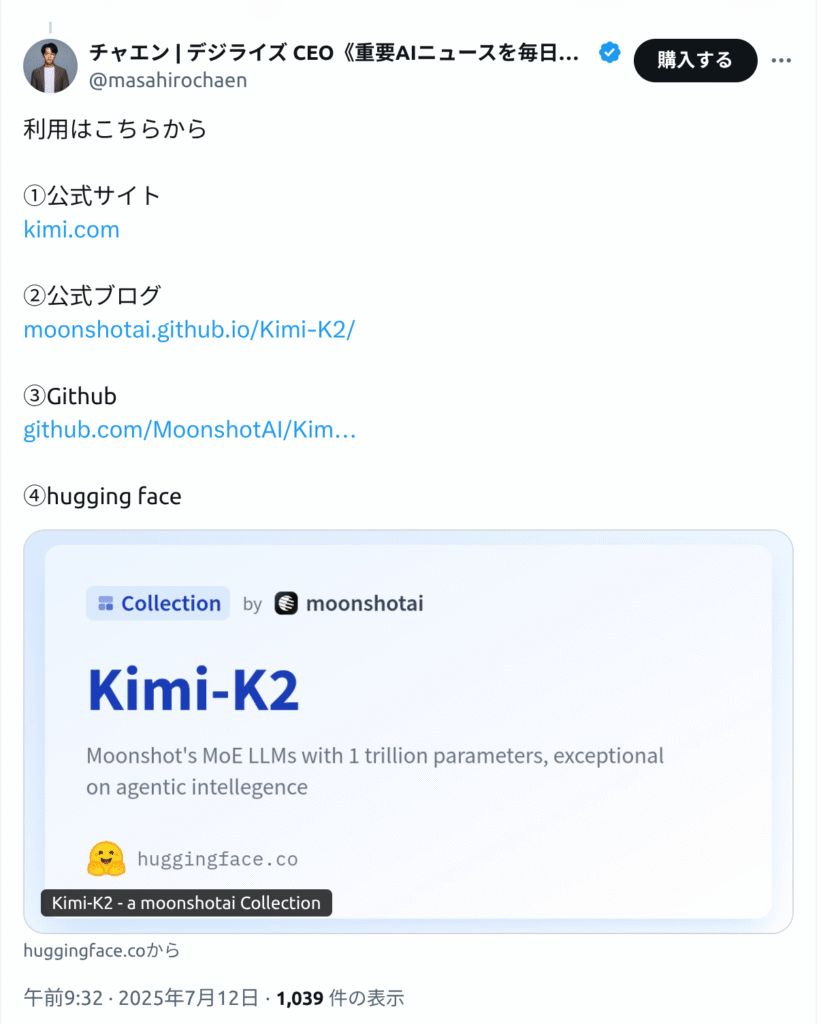
実際に職を奪うAIも登場している
たとえば、オンラインショップ構築サービス「Dukaan」では、AIチャットボットをカスタマーサポートに導入したことで、スタッフの90%が解雇された。
https://gigazine.net/news/20230712-ai-chatbot-customer-support
これにより、顧客対応の時間は2時間からわずか3分に短縮されたという。
人間よりもAIの方が圧倒的に効率的だった結果だ。
最後に
AIは確かに進化している。
しかし、それが「誰でも稼げる夢のツール」になるには、まだ遠い。
VibeCodingのような初心者向けのツールは、“最初の入口”としては機能するかもしれないが、それだけでプロ品質の仕事や収益を生むのは難しい。
学び、試し、見切りをつけ、そしてまた新しい道を探る。
今の時代に必要なのは、「使いこなす力」と「見極める力」だと感じている。
とはいえ、いくら見極めようとしても、人は完璧ではない。
情報商材に引っかかっても、誰も責任は取ってくれない。だからこそ、この世界では最終的に“自己責任”で判断していくしかない。
実際、自己責任を基本とする生き方をしている自分ですら、たまには引っかかってしまうことがある。
とはいえ、「ノーリスク」である限り「ノーリターン」でもあるのが現実。ある程度のリスクを取ることは、行動するうえで避けられない。
情報商材に引っかかる最大の理由は、「稼ぎたい」という人間の欲望が巧みに利用されているからだ。
「なんとかして稼ぎたい」「何かいい方法はないか?」という思いがある中で、「可能性があるかもしれない」と思わせる商材が目の前に現れ、さらに巧妙に作られたランディングページ(LP)の文章で背中を押されてしまう。
気づいたときには、購入していた──という構造になっている。
そもそも「楽して稼ぎたい」「在宅で収入を得たい」という欲がなければ、引っかかることもない。
しかし、多くの副業ビジネスは、その「楽して」「副業で少しでも収入を増やしたい」という欲を刺激してくる。
実はこれは、占いビジネスにも同じ構造が見られる。
たとえば、恋愛相談で占い師を頼る女性たちもまた、「どうしても恋愛成就したい」「復縁したい」という強い欲を持っており、そこにビジネスが入り込む。
つまり、最初に“欲”があり、それに対して“処方箋”を与える構造が成立しており、相談者が継続リピートしてしまうようにできている。
特に「どうしても復縁したいという願望の裏には、恋愛の主導権を握っていない、あるいは立場的に不利な状況に置かれていることが多い。
本来、うまくいく恋愛は、そこまで揉めることなく自然と進むことが多いからだ。
それでも占いビジネスが成立するのは、多くの占い師が顧客の“現実”を指摘しないからだ。
もし本当に誠実な占い師がいるとしたら、「可能性はかなり低いですが、それでも試したいですか?」というスタンスで接するはず。
しかし、そうしてしまうと継続リピートにならず、儲からない──だから多くは“希望を与える”商売になっている。
この構造は情報商材にも共通している。
特に情報商材は、価格設定が「詐欺かどうかの境界線」となる。
高額なもの(1万円以上)が多く、その分だけ「失敗したときのダメージ」も大きくなる。
一方で、イケハヤ氏のVibeCodingサロンは買い切り4980円。
価格帯としては微妙であり、「高すぎる」とまでは言えないが、「損をした」と感じるには十分な金額ではある。
致命的な被害というほどではないにしても、やはり損は損だ。
その価格に見合う価値がなかった場合、それは“価格以下の体験”になる。
比較として、本はどうだろうか。新書なら約1000円、単行本でも2000円ほど。中古で買えばさらに安くなる。
にもかかわらず、本は情報商材とは呼ばれない。たとえ中身が薄くても、「まぁそんなものか」で済まされる。価格設定が絶妙なのだ。
VibeCodingサロンの買い切り4980円という価格帯は、そういった意味で中途半端なゾーンにある。
高くもなく、安くもなく──「損したけど、大怪我ではない」といった感想が残りやすい。
そのグレーな感覚こそが、情報商材的な“うまい価格設計”なのかもしれない。